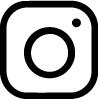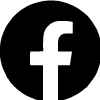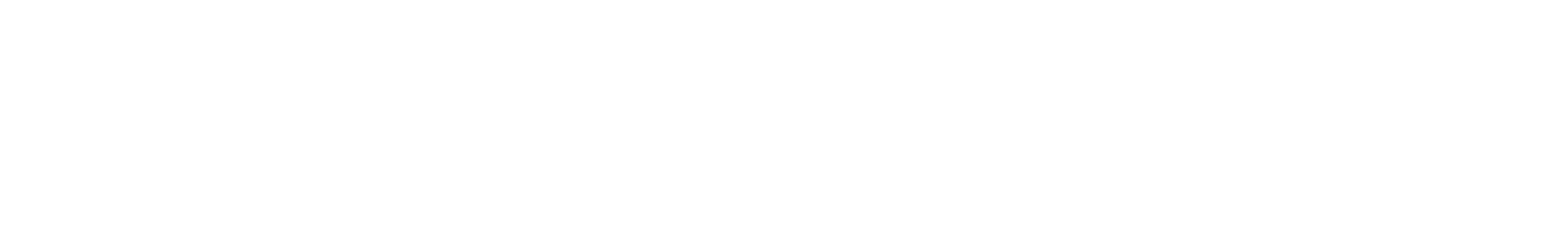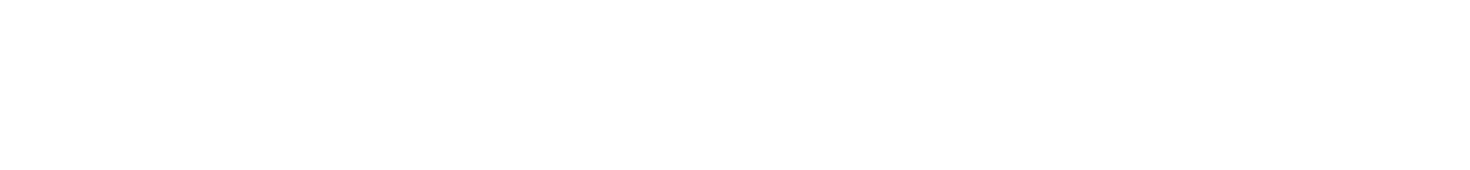開業後の運営で気づく「食材の流用」の重要性と改善の連続

カフェや飲食店の開業を目指す際、多くのオーナーが頭を悩ませるのは「どんなメニューを揃えるか」という部分です。
お客様に喜んでもらえる看板商品や、SNSで映えるメニューを用意することももちろん大切ですが、実際にお店を動かしてみると、また別の課題が浮かび上がってきます。そのひとつが 「食材の流用」 です。
オープン前のメニュー開発段階では意識が向きにくいのですが、運営を始めてしばらくすると「これは思っていた以上に重要なポイントだった」と実感される方が少なくありません。
【食材を流用できないと起こる問題】

開業して実際に厨房を回していくと、次のような問題が顕在化してきます。
-
収納スペースの圧迫
それぞれのメニューにしか使わない食材を揃えると、冷蔵庫・冷凍庫があっという間にいっぱいになってしまいます。特に小規模カフェではストックスペースが限られているため、これが大きなストレスになります。 -
食材廃棄の増加
使用頻度が低い食材は回転率が悪く、気づけば賞味期限切れ。結果的に廃棄が増え、食材コストが無駄にかさみます。 -
仕入れの複雑化
仕入れ先や発注品目が増えると、発注作業そのものが煩雑になります。スタッフが少ないお店にとっては大きな負担です。
こうした問題は、オープン前には見えてこないことが多く、「なぜか運営がうまく回らない…」と悩んでから気づくことも少なくありません。
【食材流用のメリット】

一方で、食材を複数のメニューで上手に流用できる設計にしておくと、運営は格段に効率化します。
-
在庫管理がシンプルになる
同じ食材を使い回すことで、必要な仕入れ数も安定し、在庫が把握しやすくなります。 -
廃棄が減る
使用頻度の高い食材を回すことで消費サイクルが早まり、廃棄を最小限にできます。 -
調理の効率が上がる
共通食材をベースにしたメニュー構成であれば、仕込みの段取りがシンプルになり、提供スピードも上がります。 -
アレンジや限定メニューが出しやすい
ベース食材が共通していることで、トッピングや味付けを変えるだけで新商品を開発しやすくなります。
つまり、「流用」は単なるコスト削減のためだけでなく、オペレーション効率と商品開発の柔軟性を高める手段 なのです。
【実際の工夫例】

例えばカフェ業態で考えると、次のような工夫が可能です。
-
サラダ用のチキンを、サンドイッチやパスタの具材としても使用する
-
デザートのホイップクリームを、ドリンクメニューのトッピングにも活用する
-
季節のフルーツをスイーツとスムージーの両方に展開する
-
スープに使う野菜を、キッシュやパスタの具材に転用する
「一石二鳥」「三方向に展開できる」食材を意識しておくと、メニューの幅を保ちながらも効率的な運営が可能になります。
【開業後は改善の連続】

ただし、いくら事前に考え抜いたとしても、実際にオープンしてみないと分からないことは必ず出てきます。
「このメニューは思ったより出ない」「逆にこの商品ばかり出て仕込みが追いつかない」といった現場のリアルな声に直面し、軌道修正を繰り返していくのが飲食店運営の常です。
つまり、 カフェ経営は「オープンしたら完成」ではなく、「オープンしてからがスタート」。
その後は「改善の連続」であり、日々の営業の中で気づいた課題を、ひとつひとつ修正していく姿勢が必要です。
【まとめ】

カフェや飲食店の開業後に気づく「食材の流用」というポイントは、効率的な店舗運営に直結する大切な視点です。
収納スペース、食材廃棄、仕入れの手間、調理効率…。これらの課題は、共通食材を設計に組み込むことで大きく改善できます。
そして大前提として、開業後はどんなに準備をしても想定外の出来事が次々と起こります。だからこそ、 「改善を続ける気概」こそが長く愛されるお店を育てる力 になります。
カフェ経営を目指す方は、ぜひメニュー開発の段階から「流用できる食材設計」を意識し、オープン後も柔軟に改善を重ねていってください。
あわせて読みたい記事『カフェの原価率ってどのくらい?』

【執筆者】
CREATIVEDEVELOPMENT株式会社
代表取締役
伊藤栄一
飲食店メニュープロデューサー、カフェメニュー開発・開業支援
『メニューの開発実績500種類以上』『専門学校で講師の実績』カフェの現場で5年間シェフを歴任し、様々なメニュー開発を行う。開発メニューの中には、テレビや雑誌に取り上げられた事例も。