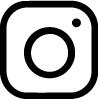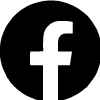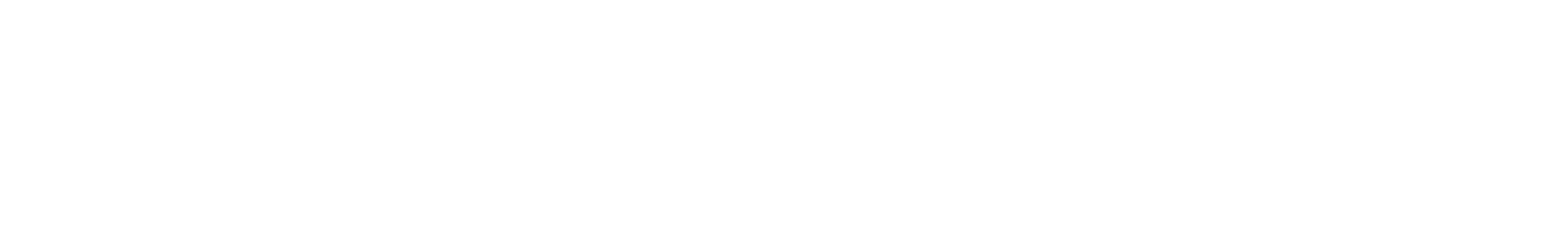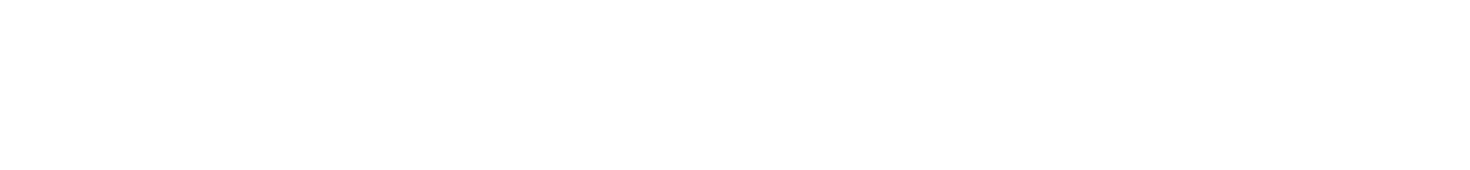売れるメニューを作るために必要な視点とは?
〜情報収集とトレンド分析の重要性〜

カフェを運営する中で、「どうすれば売れるメニューが作れるのか?」という問いは常にオーナーや料理人の頭を悩ませるテーマです。
おいしい料理を提供することはもちろん大前提ですが、それだけでは売上に直結しないのが現実です。見た目の華やかさや話題性が必要な場面もあれば、逆に安定した定番性が求められる場合もあります。
このように、味やビジュアルのクオリティだけでなく、マーケットの変化や消費者のトレンドを常に意識し、それを開発に反映させていくことが欠かせません。今回は、売れるメニューを生み出すために必要な情報収集の方法や、具体的な分析の視点について解説していきます。
【味と見た目だけでは足りない理由】

飲食業界では「料理がおいしければ自然とお客様は集まる」という考え方が根強くあります。しかし実際には、おいしいお店が淘汰されていく事例は後を絶ちません。理由はシンプルで、「おいしいお店」が今や世の中に溢れているからです。
例えば、SNSが普及した今は、誰もが口コミや写真を通じて新しい店や人気店の情報を手軽に発信できます。すると「おいしい」ことはもはや当然であり、差別化要素にはなりにくいのです。さらに、消費者の関心は「健康志向」「映え」「地域性」「サステナビリティ」など、時代ごとに変化していきます。
つまり、「今のお客様が求めているポイント」にメニューを合わせていかなければ、売れるメニューにはなりづらいのです。
【売れるメニュー作りに欠かせない「情報収集」】

トレンドをメニューに反映させるためには、まず情報収集が欠かせません。ここで大切なのは、ただ流行を追いかけるのではなく、自店のコンセプトや顧客層に適した形で取り入れることです
。
1. 人気店に足を運ぶ
まず実践しやすいのが、同業他社の人気店や同じエリアで繁盛している異業種のお店を訪れることです。
繁盛しているお店には、必ず繁盛している理由があります。単に「料理がおいしいから」ではなく、価格設定・盛り付け・オペレーション・内装・接客など、複数の要素が一体となって支持されています。
特にメニューに注目する場合は、以下の視点で分析すると効果的です。
-
どのメニューが売れ筋なのか?(周りの注文状況やメニュー表の記載方法から推測)
-
価格帯の中心はどこに設定されているか?
-
盛り付けや食器はどう工夫されているか?
-
メニュー名に工夫はあるか?(キャッチコピー的な役割)
これらを一つひとつ分解していくと、自店に取り入れられるヒントが見つけられるはずです。
2. SNS・メディアのチェック
InstagramやTikTokでは、日々新しい飲食トレンドが生まれています。特にZ世代を中心とした若年層の消費者は、SNSで「食べたい」と思ったものを実際に体験する行動力があります。
「#カフェ巡り」「#新宿ランチ」などのハッシュタグ検索をしてみると、どのような料理や演出が注目されているのか一目で分かります。また、グルメ系インフルエンサーや食に特化したメディアの発信を追いかけるのも有効です。
3. 展示会や業界紙の活用
外食産業の展示会や、食材・飲料関連の新商品発表会などに足を運ぶのも方法のひとつ。業界の大きな潮流をつかむには、こうした場での情報収集が有効に働きます。
例えば「プラントベース」などは、ここ最近での展示会では、目立つキーワードのひとつになっています。
【売れるメニューを生み出す「分析の視点」】

情報を集めただけではまだ不十分です。重要なのは、そこから「自店にどう落とし込むか」を考えることです。
-
ターゲットに合っているか?
例:健康志向の層が多い立地なら、低糖質・高タンパクを意識。 -
コンセプトとブレていないか?
例:和カフェなのに突然韓国スイーツを入れると違和感。 -
価格帯の整合性があるか?
例:ドリンクは500円前後なのに、デザートが2,000円だとバランスが悪い。 -
オペレーションに無理がないか?
例:トレンド要素を入れても仕込みや提供に時間がかかりすぎると、現場が回らない。
これらを丁寧に検討し、自店ならではの「売れる形」に落とし込んでいくのです。
【トレンドを“取り入れる”のではなく“活かす”】

最後に強調したいのは、「トレンドはそのまま真似するものではない」という点です。トレンドを追いかけすぎると、どうしても“二番煎じ”感が出てしまいます。重要なのは、自店の強みやコンセプトに合わせてアレンジし、オリジナリティを持たせることです。
例えば、流行しているスイーツをそのまま再現するのではなく、地元の食材と組み合わせたり、健康志向に寄せたりと、自店ならではの解釈を加えることで「ここでしか食べられない」という価値を作ることができます。
【まとめ】

売れるメニューを作るためには、味や見た目の工夫だけでなく、常に市場の変化を意識し、情報収集と分析を繰り返す姿勢が必要です。人気店に学び、SNSや展示会でトレンドを把握しつつ、それを自店のコンセプトに落とし込む。このプロセスを続けることで、時代に合った“売れるメニュー”が生まれていきます。
「儲かるメニュー」を作るのではなく、「お客様に求められるメニュー」を作る。そうした発想こそが、カフェ経営における最大の武器となるのです。
あわせて読みたい記事『メニュー表にマーケティング戦略を 』

【執筆者】
CREATIVEDEVELOPMENT株式会社
代表取締役
伊藤栄一
飲食店メニュープロデューサー、カフェメニュー開発・開業支援
『メニューの開発実績500種類以上』『専門学校で講師の実績』カフェの現場で5年間シェフを歴任し、様々なメニュー開発を行う。開発メニューの中には、テレビや雑誌に取り上げられた事例も。