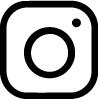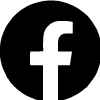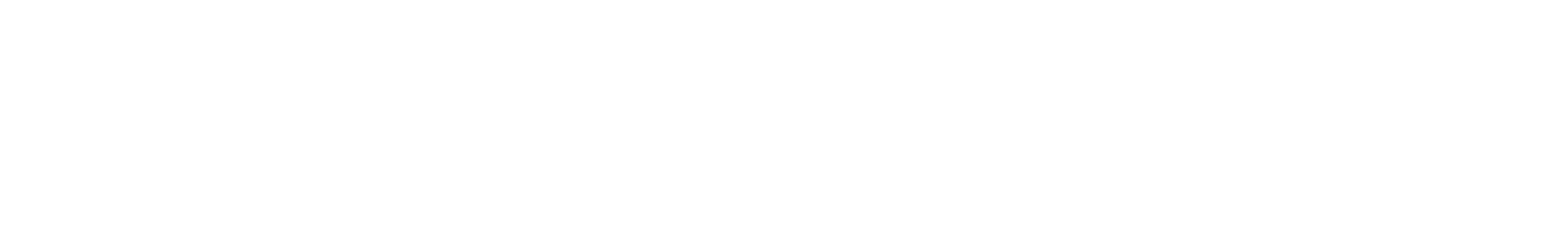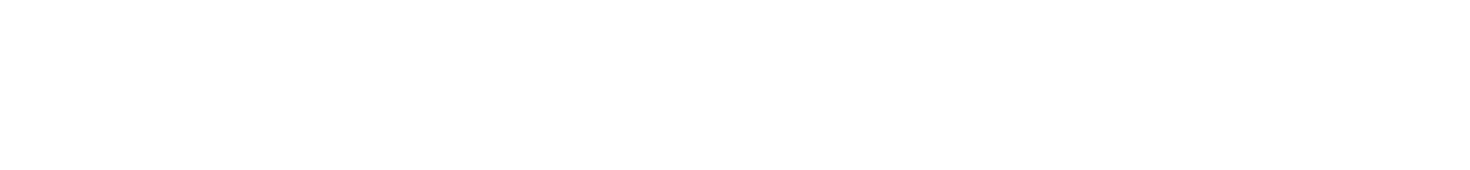【カフェのメニュー改善】単なる新商品追加ではなく、時間帯×顧客ニーズから考える改善の本質

カフェにおいて、メニューはお客様に提供する価値そのものです。そしてその改善は、ただ「新しい商品を作り、入れ替えればよい」というものではありません。
真に「効果的なメニュー改善」とは、時間帯ごとの顧客ニーズに応じて、誰に、どんな価値を届けたいのかを明確にした上で行うべきものです。その戦略構築ができてはじめて、売れるメニューへの道が開けます。
この記事では、戦略的なメニュー改善の進め方を解説していきます。
【メニュー改善の前に「目的を明確にする」ことの大切さ】

開業後に多くのお店が陥る典型的な間違いがあります:
-
新商品を出すこと自体に満足し、結果的に売れない…
-
ありきたりな商品ばかりで飽きられてしまう…
-
品数が増えすぎて在庫やオペレーションが崩壊する…
どれも「新しさ」に偏重した対応で、多くは顧客視点や現場の実情が抜けているために起こります。
本来必要なのは「新メニューのコンセプト設計」から始めて、その後に具体的な商品開発に進むアプローチです。
【時間帯 × 顧客ニーズ でメニューを構成する構造】

1. 「いつ」誰が来て、何を求めているかを整理する
-
モーニング(朝):出勤直前のサラリーマン → 「気軽さ・スピード・通い続けれる価格」
-
ランチタイム:近隣オフィスや女性グループ → 「飽きない・スピード・価格の納得感」
-
カフェタイム:主婦や休日訪問者 → 「リラックス・スイーツ・居心地」
-
ディナータイム:仕事帰りや友人グループ → 「会話を楽しむ・飲み物の選択肢・量の調整」
まずはあなたのお店の現状の時間帯別顧客像を明確にし、それぞれの時間帯で「誰に」「どんな体験」を届けたいのかを設定することが、戦略の土台になります。
2. ニーズに対応する商品構成を検討する
-
上記のターゲットに対して、どのような商品やセット構成が効果的かを設計します。
-
例えば、「忙しい朝」にはクイックな軽食、「カフェタイム」にはティーフリーメニューやスイーツのセットなど。
3. それを踏まえて具体的な商品開発へ
-
ターゲットと体験設計が定まって初めて、「具体的なメニュー(商品名、価格、見せ方)」を検討します。
-
見た目、原価率、オペレーション負荷も考慮に入れて、戦略的に設計することが必要です。
【メニュー改善の際に注意したいポイント】

-
時間帯ごとの提供能力を確認する
ピーク時に提供スピードが落ちてしまう構成は、評価の低下にもつながります。提供までの時間を改善計画に含めましょう。 -
固定化せず、PDCAを回すこと
実装後も定期的に振り返り、不要なものは削除、目立たせるものは追加など、改善の再設計を行うことが重要です。 -
スタッフの理解と協力を得る設計にする
新メニューはオペレーションや販売促進に影響を与えます。現場のスタッフ理解と協力を得て実装することが成功の鍵です。
【まとめ:「目的」あっての「メニュー改善」】

多くのカフェが直面する誤解は、「良い商品を作れば良い成果につながる」と考えてしまう点です。
しかし本質は、「誰に」「いつ」「何を提供したいのか」です。
新しい商品を考えるのはそのあとでしかありません。
顧客ニーズや時間帯の分析に基づいた戦略的アプローチから、ぜひ「戦えるメニューづくり」を始めてください。
【おわりに】

CREATIVE DEVELOPMENTでは、時間帯別顧客分析とメニュー設計を組み合わせた、戦略的な商品開発支援を行っています。
「メニュー改善の流れを体系化したい」「数字に基づいた根拠を持ちたい」という方は、お気軽にご相談ください。
あわせて読みたい記事『【カフェメニュー】売れるメニュー開発の流れ 』

【執筆者】
CREATIVEDEVELOPMENT株式会社
代表取締役
伊藤栄一
飲食店メニュープロデューサー、カフェメニュー開発・開業支援
『メニューの開発実績500種類以上』『専門学校で講師の実績』カフェの現場で5年間シェフを歴任し、様々なメニュー開発を行う。開発メニューの中には、テレビや雑誌に取り上げられた事例も。