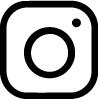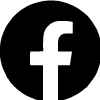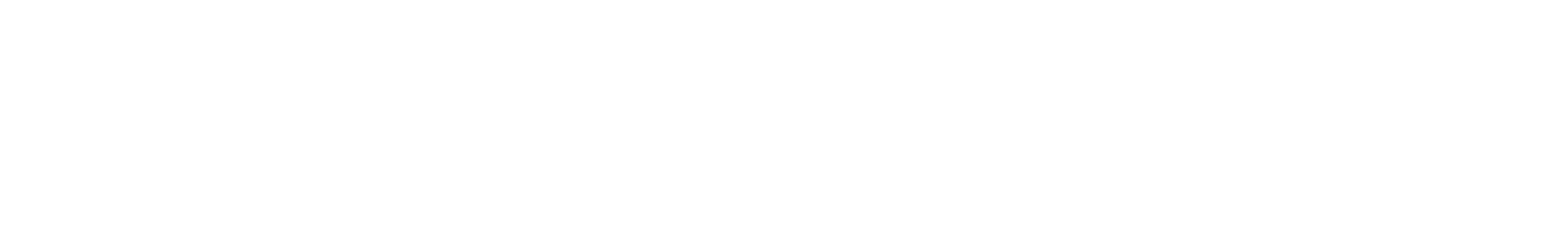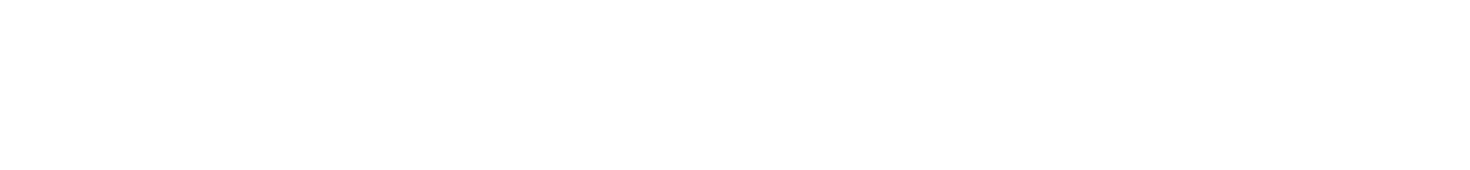【メニュー開発の落とし穴】オペレーションを見据えた設計が、カフェの命運を分ける

カフェの現場で起こりがちな「あるある」のひとつに、「商品自体は素晴らしいのに、オペレーションが回らずに評価が落ちる」というケースがあります。
たとえば、「ちょっと混雑しただけで、料理の提供までに40〜50分待たせてしまった」というような事態。
実際、開業前にはなかなか実感できないことかもしれませんが、この問題は非常に深刻で、カフェの評価・リピート率・スタッフの負担など、あらゆる部分に影響を与えます。
本記事では、オペレーションを見据えたメニュー開発の重要性について掘り下げてご紹介します。
【なぜ「味」や「ビジュアル」だけでは足りないのか?】

メニュー開発の段階では、「この料理は美味しい」「見た目が映える」といった視点が優先されがちです。もちろんこれらは商品力としてとても大事な要素ですが、それだけで成り立つほど飲食業は甘くありません。
いくら美味しくてSNS映えしても、来店から提供までに40分以上待たされると、お客様の評価は急激に下がってしまいます。
特にランチ帯などのピークタイムは、滞在時間が限られているケースが多く、「遅い店」というレッテルを貼られてしまうリスクもあります。
【メニュー開発段階で見落とされがちな「オペレーション設計」】

●1. 同時注文時の処理能力を想定していない
たとえば、1口のコンロしかないのに、3品オーダーが入った際にすべてそのコンロを使う設計だと、同時間帯に注文が集中した場合、すぐにボトルネックが発生します。
このように、キッチンのキャパシティを無視したレシピは、開業後の現場で必ず詰まるのです。
●2. 盛り付け工程が複雑すぎる
「最後に複数のハーブをトングで整え、ソースをディスペンサーを使い絵柄を施す」など、細かい作業が複数あると、それだけでオーダーが詰まります。
限られた人数で回す飲食店においては、再現性と効率性が何よりも大切です。
【理想は「美味しい × 早い × 誰でもできる」】

開発するメニューがこの3点を満たす設計になっていれば、繁忙期にもクレームなく回すことができ、評価も安定していきます。
◎美味しい:
もちろん商品のクオリティは大前提。ただし、「手間をかけないと美味しくならない」は危険信号。誰が作っても一定の品質が保てるように調整を。
◎早い:
盛り付け含めて1品あたり3〜5分以内に仕上がるかを目安に。作業フローに無駄がないか、事前仕込で注文後の時間を短縮できないかなど、開発段階から意識して設計すること。
◎誰でもできる:
新人スタッフでも再現できるよう、マニュアルやレシピを数値化するのが理想です。たとえば、ソースの量や焼成時間をグラムや秒単位で統一するなど。
【提供スピードは「ブランド力」にも直結する】

「待たせない」というのは、ブランドに直結する体験要素のひとつでもあります。
お客様が「また来たい」と思う理由の中には、「安心して利用できる」「いつも一定のスピードで出てくる」という無意識の快適さが含まれています。
逆に、どれだけ世界観が良くても、毎回待たされたり提供順がバラバラだったりすると、お客様の満足度は下がり、スタッフの士気も削がれてしまいます。
【商品開発時に見直したいチェックポイント】

・提供時間は何分目安か?
・ピーク帯の注文集中時に耐えうるか?
・人員が1人欠けても回せる設計になっているか?
・新人スタッフでも再現できるレシピか?
・調理や仕込みに、過剰な手間がかかっていないか?
これらを事前にチェックしながら開発を進めることで、「開店後に慌ててメニュー改修」という事態を防ぐことができます。
【まとめ:オペレーションから逆算して考える】

メニュー開発は、単なる「美味しい料理」を考えるだけでなく、お店全体の運営をスムーズにする設計でもあります。
スタッフの動き、キッチンのキャパ、時間の流れ。これらをトータルで捉えて初めて、“売れる商品”が完成するのです。
「少し混んだだけで40分待ち」になるような設計では、どれだけ味が良くても飲食ビジネスとしては成立しません。
オペレーションに強いメニューこそが、実は最も優れたメニューなのです。
あわせて読みたい記事『原価の適正管理をするためにやるべきこと』

【執筆者】
CREATIVEDEVELOPMENT株式会社
代表取締役
伊藤栄一
飲食店メニュープロデューサー、カフェメニュー開発・開業支援
『メニューの開発実績500種類以上』『専門学校で講師の実績』カフェの現場で5年間シェフを歴任し、様々なメニュー開発を行う。開発メニューの中には、テレビや雑誌に取り上げられた事例も。