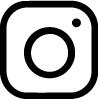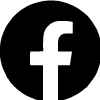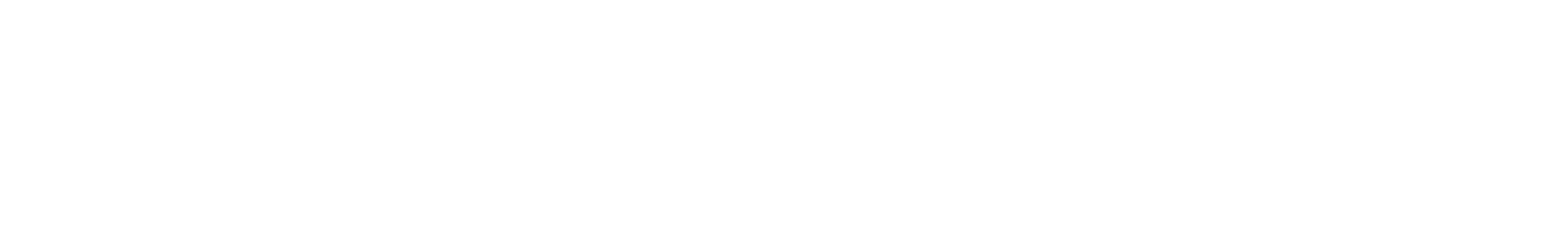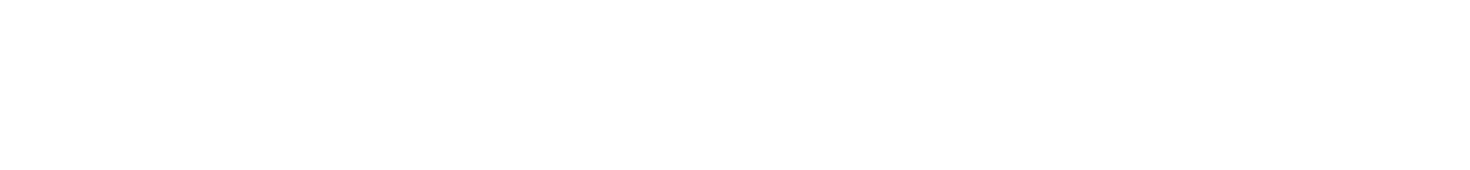食材価格の変動を見越した売価設定を—「原価が合わない」を防ぐための考え方

カフェ経営において「原価管理」は避けて通れないテーマです。
特に、鮮魚や青果といった生鮮食材を扱う場合には、日々の仕入れ価格が変動することが前提になります。
開業前にメニューを設計し、理想的な原価率で売価を決めたとしても、オープンして数ヶ月経つと「想定していた利益が出ていない」ということは珍しくありません。
その要因のひとつとして、“価格変動リスク”を織り込めていなかったことが考えられます。
今回は、カフェ開業時に見落とされがちな「価格変動を前提とした売価設定」について、実務的な視点から解説します。
1. 原価は固定ではない—生鮮食材の特性を理解する

飲食業をはじめたばかりの方が誤解しやすいのが、「食材原価は常に一定」という考え方です。
たとえば、次のような食材は季節や天候、需給バランスによって価格が大きく変動します。
-
鮮魚類:漁獲量や季節要因により日々価格が変化
-
青果類(特に葉物・果物):天候や輸送状況に左右されやすい
-
乳製品や卵類:輸入コストや飼料価格によって変動
つまり、「原価率30%で設計したはずのメニューが、いつの間にか33%を超えていた」などの状況は、実はこのような仕入れ特性からくるものなのです。
2. 可変要素を織り込んだ価格設計が必要

価格変動が起きることを前提に、“可変原価”を想定した売価設定を行うことが重要です。
例えば、次のような設計をするとよいでしょう。
| 項目 | 設計方法の考え方 |
|---|---|
| 安定食材(乾物・加工品など) | 固定原価として扱う |
| 変動食材(青果・魚介類など) | 上下2〜3%の変動幅を想定 |
| トータル原価率 | 平均で設定(高騰時でも許容範囲内に収まるように) |
このように、原価の中に「変動余地」をあらかじめ持たせておくことで、多少の仕入れ変動にも耐えられる設計になります。
また、食材の中でも“変動の激しい素材”を主役に据える場合には、期間限定メニューとして運用するのも一つの方法です。そうすれば、価格調整やメニュー入れ替えも柔軟に対応できます。
3. 原価を守るための「メニュー構成」と「バランス」

売価設定を安定させるためには、単にひとつのメニューを最適化するだけでなく、メニュー全体のバランス設計も必要です。
例えば、
-
原価率が高めの「主力商品」
-
原価率を抑えられる「利益確保メニュー」
-
価格調整しやすい「季節限定メニュー」
といったように、構成の中で“収支のバランスをとる”考え方が求められます。
具体的には、
-
メイン商品で利益率を落としても、ドリンクやスイーツでカバーする
-
高騰しやすい素材を使用するメニューは、数量限定または季節商品にする
-
原価率の安定しているサイドメニューを軸に据える
といった運用で、全体原価率を一定の範囲にコントロールすることが可能になります。
4. 原価ズレを防ぐための実務ポイント

売価設定をうまく行ったとしても、実際の運営で調整ができなければ意味がありません。
以下のような仕組みを日常的に取り入れていくと、原価ズレを防ぐことができます。
▷ 仕入れ価格の定期チェック
毎月1回など、仕入れ単価を更新して変動を把握しておく。
「いつの間にか上がっていた」という状況をなくします。
▷ メニュー別の原価率確認
看板商品・日替わり・サイドなどカテゴリー別に原価率を管理。
実際の販売比率と合わせて粗利を把握することで、調整判断がしやすくなります。
▷ 仕入れ先との関係構築
良い取引先は“安定供給”という形でリスクを減らしてくれます。
仕入見込量などを提示しながら、取引先にも「これだけ買ってもらえるなら」と思ってもらうことが、良い関係性構築にも繋がります。
▷ 原価率を見てメニューを変える柔軟性
季節によって材料コストが上がる時期には、思い切って別の素材に切り替える判断も必要です。
5. 「あれ?なんか合わない」とならないために

開業後しばらく経つと、「想定していた利益が出ていない」というケースに多くのオーナーが直面します。
そのとき初めて「原価が合わない」と気づくわけですが、実際には“最初の売価設計”に問題があることがほとんどです。
-
食材価格の変動を見越していなかった
-
原価率のバランス設計をしていなかった
-
実際の販売比率と想定がズレていた
こうした事態を防ぐためにも、開業時から「可変原価」を意識して設計することが大切なのです。
まとめ:売価設定は“現場感覚”が鍵

売価を決める際は、理想的な原価率の計算だけでなく、「どんな素材を使うのか」「どんな調達環境なのか」まで踏み込んで考える必要があります。
つまり、
売価設定は机上の計算ではなく、現場を知る経営判断である。
ということです。
とくに鮮魚や青果を扱うお店では、日々の仕入れ状況に応じて調整が必要になるため、
「変動を見越した売価設計」
「バランスの取れたメニュー構成」
「定期的な原価モニタリング」
この3点をセットで考えることが、長期的な安定経営への近道です。
カフェや飲食店の開業準備では、ついデザインやメニュー構想に意識が向きがちですが、こうした“地味な数字管理”こそ、後から効いてくる実務の要なのです。
あわせて読みたい記事『カフェの食材仕入先の選定方法 』

【執筆者】
CREATIVEDEVELOPMENT株式会社
代表取締役
伊藤栄一
飲食店メニュープロデューサー、カフェメニュー開発・開業支援
『メニューの開発実績500種類以上』『専門学校で講師の実績』カフェの現場で5年間シェフを歴任し、様々なメニュー開発を行う。開発メニューの中には、テレビや雑誌に取り上げられた事例も。