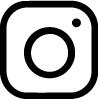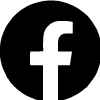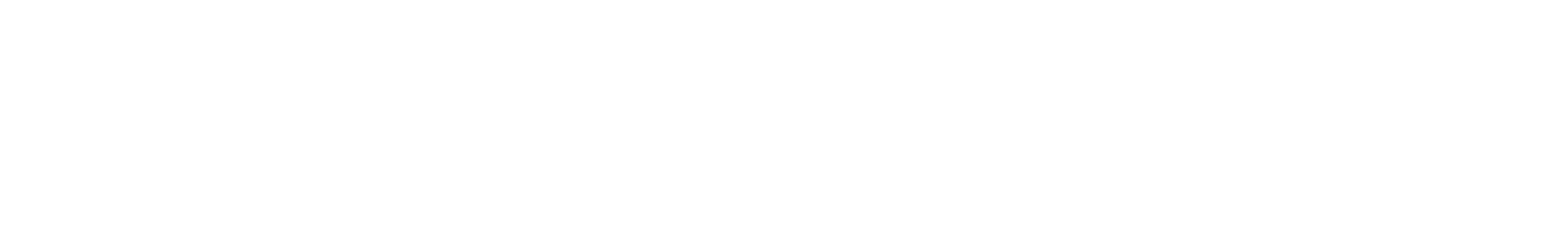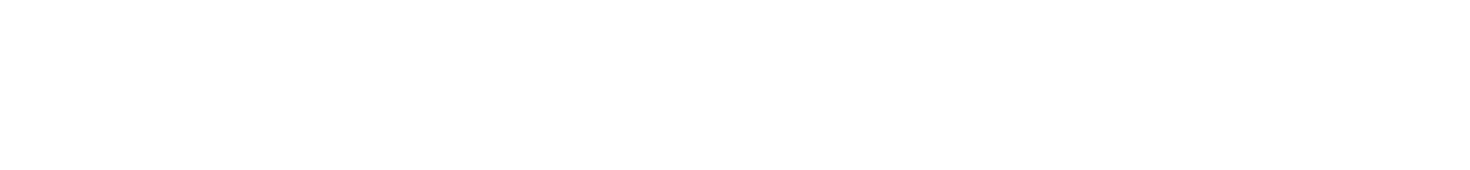カフェ開業で失敗しないための「収納キャパ」とメニュー設計の関係性

カフェや飲食店を開業するとき、多くのオーナーが注目するのは「立地」や「メニュー」、そして「内装デザイン」かもしれません。
しかし実際に運営が始まってから痛感するのが、厨房内の収納キャパシティ です。
特に冷蔵庫や冷凍庫の容量は、店舗の効率性を大きく左右する要素であり、これを軽視してしまうと開業後に大きなストレスやロスにつながります。
では、収納キャパをどう考えるべきなのか。その答えは、メニュー構成と使用食材から逆算することにあります。
【なぜ「逆算」が必要なのか?】

厨房の設計段階では、つい「大きめの冷蔵庫を入れておけば大丈夫だろう」と考えてしまいがちです。
しかし実際には、扱う食材の種類や仕込み方法によって必要な容量は大きく変わります。
例えば、
- サラダやサンドイッチを多く扱う → 葉物野菜が大量に必要になり、カサが大きく冷蔵庫を圧迫する
- デザートを多く展開する → 冷凍庫にアイスクリームや冷凍フルーツ、ケーキのストックが必要になる
- ドリンクメニューを充実させる → 牛乳や豆乳、シロップ類の保管スペースが必須になる
つまり、「どんなメニューを提供するか」によって必要なストレージの内容は大きく変わり、逆算を怠ると「物が入りきらない」「仕入れが回らない」といった問題に直結してしまうのです。
【葉物野菜の落とし穴】

特に注意が必要なのは、サラダや軽食に欠かせない 葉物野菜 です。
葉物はカサが出やすく、さらに仕入れた状態と仕込み後の状態で二重に場所を取ります。
たとえば、仕入れたレタスを保管しておくスペースと、それを洗ってカットし、仕込み済みとして保存するスペースの両方が必要になるのです。
「見た目よりもはるかにスペースを食う」典型的な食材であり、開業前に十分に想定していないと、オープン後に冷蔵庫が常にパンパンで回らない…という事態に陥ります。
【厨房設計で考えるべきポイント】

収納キャパを考慮した厨房設計をする際には、以下のポイントを押さえておくと失敗が少なくなります。
-
メニューの軸を決める
サラダ中心なのか、デザート中心なのか、ドリンク中心なのか。軸によって必要な冷蔵・冷凍の比率は変わります。 -
仕込み工程をイメージする
「仕入れた状態 → 下処理 → 仕込み済み保存 → 提供」と流れを具体的に描き、その各段階でどのくらいの容量が必要かを算出します。 -
ピーク時の在庫量を想定する
平日のランチピークや休日のカフェタイムなど、最も仕込みやストックが必要な時間帯を想定し、そのときに十分余裕があるキャパを確保することが重要です。 -
回転率を考慮する
使用頻度が高い食材は回転率が高いため、それに合わせた容量と取り出しやすさを重視します。
【収納不足が引き起こす運営トラブル】

もし収納キャパの見積もりを誤ると、次のような問題が発生します。
-
食材が入りきらず、追加の冷蔵庫を購入して無駄なコストが発生
-
在庫が整理できず、必要なものが近くに置けないことでオペレーションが混乱
-
スタッフの作業効率が下がり、提供時間が遅延する
つまり、収納を甘く見積もることは「売上機会の損失」や「経費の増加」に直結するのです。
【改善と調整の連続】

もちろん、開業時点で完璧なキャパ設計をすることは難しいものです。
実際に営業を始めると、「このメニューは想定以上に出る」「この食材は思ったより動かない」といったギャップが必ず生まれます。
重要なのは、現場で出てきた課題をもとに改善を重ねる姿勢です。
-
ストックの仕方を見直す
-
メニューを微調整して食材を流用しやすくする
-
使用頻度の低い食材を外して効率化する
こうした改善を繰り返すことで、収納キャパの問題も次第に解消されていきます。
【まとめ】

カフェ開業における冷蔵庫・冷凍庫の収納キャパは、単なる「設備の大きさ」の問題ではなく、メニュー設計と直結する経営課題です。
葉物野菜のように予想以上にスペースを取る食材もあり、仕入れから仕込み、提供までの流れを逆算して容量を設計することが欠かせません。
そして、どれだけ準備をしても想定外の事態は起こるもの。大切なのは、「改善を繰り返しながら最適化していく」という意識を持ち続けることです。
収納キャパを軽視せず、メニュー開発と厨房設計をリンクさせて考えることで、開業後の運営をスムーズにし、無駄のない経営につなげていきましょう。
あわせて読みたい記事『カフェの食材仕入れについて』

【執筆者】
CREATIVEDEVELOPMENT株式会社
代表取締役
伊藤栄一
飲食店メニュープロデューサー、カフェメニュー開発・開業支援
『メニューの開発実績500種類以上』『専門学校で講師の実績』カフェの現場で5年間シェフを歴任し、様々なメニュー開発を行う。開発メニューの中には、テレビや雑誌に取り上げられた事例も。